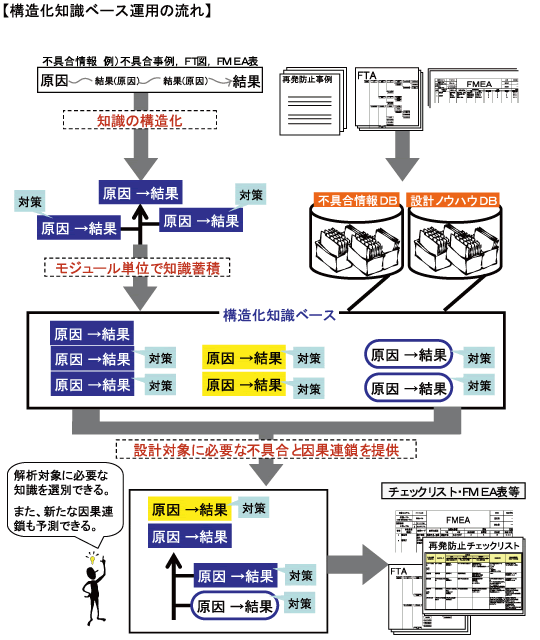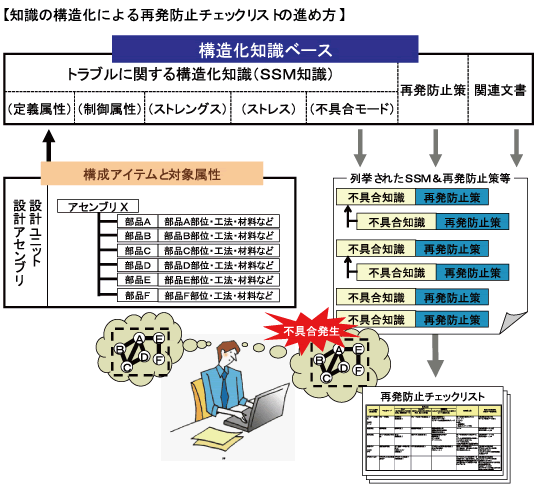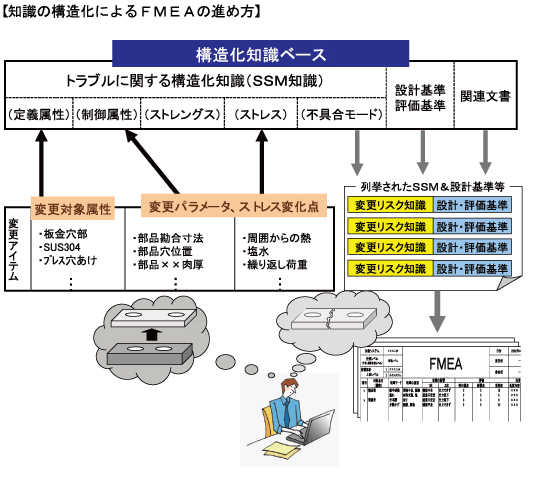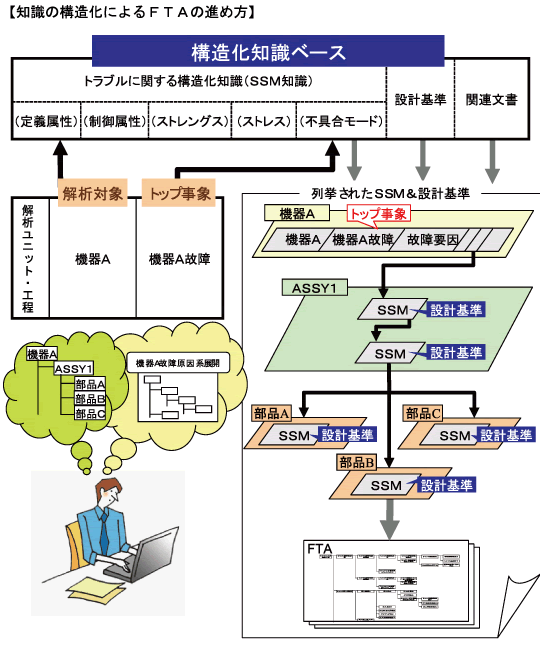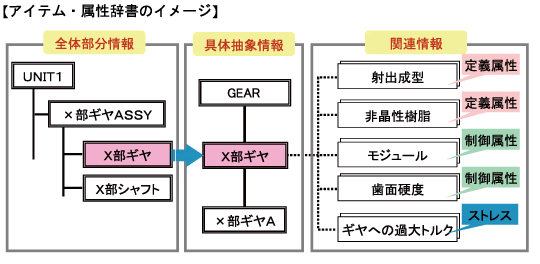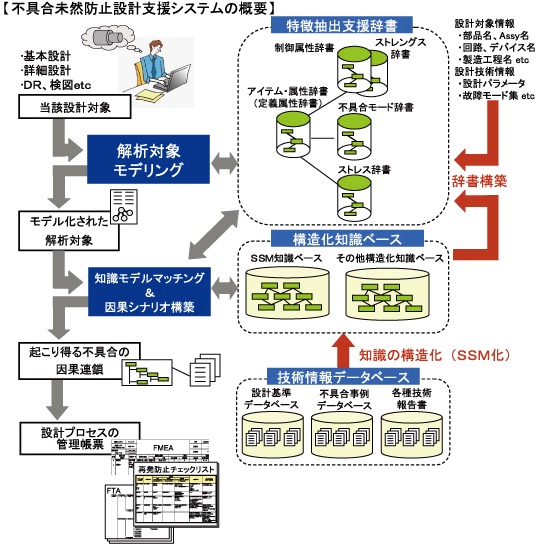設計者・技術者は、自分の経験や他人の経験から、将来に使えるトラブルの知識(教訓)を抽出し、その知識を次の開発アイテムに対してうまく適用し、その開発アイテムにトラブルが起こるのではないかと連想することで、その開発アイテムに起こりうるトラブルを予測する(気付く)ことができます。
他人の経験から学ぶことは容易なことではありません。しかし、製品の構成が複雑になり、その一方で部品や材料などに関する仕様の共通化・再利用が進む設計/製造現場では、設計者・技術者は、自己の経験だけでは未然防止はおろか再発防止すら困難な状況になっています。
したがってトラブル知識を活用して未然防止を実現するには、組織が共有するトラブル情報を活用したトラブル知識ベース支援が欠かせないものとなっています。
しかし、設計・生産技術・製造などの各部署が保有するトラブル情報(過去の不具合事例、クレーム情報、FT図、FMEA表など)を、そのトラブル情報の文書のまま活用しようとしても限界があります。トラブル情報から将来の予測に再利用できるように知識・教訓を抽出し、それを構造的に整理すること(知識の構造化)が必要です。(詳しくは、「トラブル未然防止のための知識の構造化」を参照ください。)
SSMの観点を利用して知識の構造化を進め、構造化知識ベースを構築し、各知識に設計ノウハウや関連事例などをリンクして閲覧できるようにしておくと、トラブルに関する知識・情報基盤を構築することができます。(詳しくは、「SSMとは-トラブル知識の構造化モデル-」を参照ください。)
構築されたトラブルに関する構造化知識は、下図のように、文書の形式は異なっていても、共通の知識プラットフォーム(構造化知識ベース)に登録されます。構造化知識ベースを活用すれば、設計者は、元の文書形式を意識することなく、未然防止活動における具体的なニーズ・目的に沿って設計アイテムに必要なトラブル知識を端的に収集し、トラブル予測・未然防止を進めることができます。また知識は構造化されているため、うまく構造の要素を並び替えて、設計管理帳票(FMEA表、FT図、チェックリスト表など)に柔軟に反映させることができます。